エーテルとダークマター[物理]
2008年9月6日(土) 今井憲一教授
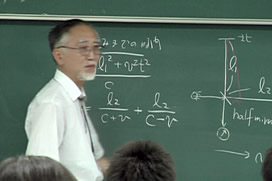
皆さん、こんにちは。京都大学理学研究科の今井です。
わたしは、この最先端科学の体験型学習講座という、日本科学振興機構、JSTの委託を受けた授業として理学部が行うもの。京都大学理学部が行う授業でして、これから1か月、ああ、1年間ですね。毎月最初の第1土曜日に、当理学研究科の教員が講義を、一般向けの講義をいたします。
特に高校生を対象としてということでございます。で、まずそれのトップバッターとして、私が今日お話をします。私は、専門は原子核物理学というのを専門にしております。この間の7月のときには、そういう素粒子と原子核というお話をしましたけれど、今日はちょっと違うテーマでですね、「エーテルとダークマター」というタイトルでお話をします。
この中で、エーテルとダークマターって初めて聞いたっていうかた、どのぐらいいらっしゃいます? ああ、みんな初めてだよね。エーテルというのは、エチルエーテルとは違いますよ。ここでいうのはね。薬品のエーテルではないんです。今から百数十年前ですね、ちょうど日本が幕末から明治の時代ですね。約半世紀、50年近くですね、当時のすべての物理学者は、宇宙はエーテルで満たされていると信じて疑いませんでした。エーテルという物質が何かっていうことは、それが分かったわけじゃないんだけど、そういうものが宇宙を満たしているというのを信じて疑わなかった。
だから、19世紀末ぐらいのいろんな、特にヨーロッパの小説なんか読みますとですね、登場人物が、「宇宙はエーテルで満たされてる」っていうようなことが書いてあります。要するに、物理学者だけでなくて当時の人々は、多分、物理学者から教えられて、宇宙はエーテルで満たされてると信じてたんです。 で、このエーテルっていうのは、英語では「イーサー」と読みます。皆さん、「イーサーネット」っていうネット、コンピューターのネットワークの名前、聞いたことあります? イーサーネットっていうのはコンピューターのネットワークで、すべてがあらゆるところにあるという、そういうのを意味してイーサーネット、エーテルネットといってるわけですね。
エーテルの歴史的な物語
だから、話の前半は、そのエーテルの物語を少し歴史的にお話ししますね。歴史をたどってお話しします。で、後半はですね、ダークマター。エーテルは、アインシュタインの相対性理論によって、そんなものは必要ないということになったわけですけれども、今はそのダークマターというのが、この宇宙にわれわれが知ってる量の10倍近くあると。われわれの水素やヘリウムや、そういう星ですね。星の量に比べると10倍近くあるというのを、ほぼほとんどの物理学者が信じるようになっております。それがダークマター。それで、その研究をわれわれもやっておりますので、その話を少しさせていただきたいと思います。
ダークマターは現代のエーテルかどうかということですね。 さて、話はですね、歴史の話は、ファラデーから始まりますね。皆さん、ファラデーは知ってますよね。知らない? なかなかハンサムですよね。若いとき、これは肖像画ですね。これは写真です。当時、もう写真はできてますからね、写真です。この人は、僕が最も尊敬する実験物理学者ですね。もともとかじ屋の息子。なんか10人兄弟の何番めかという。それで、小学校を出るとでっち奉公に行って、でっち奉公へ行った先が製本屋さんだったんですね。印刷。で、本人が、本がいっぱいあるので、その本で独学をして、そして研究者に、科学者になったという人です。

で、随分たくさんの発明をしてますね。発明、発見。いちばん有名なのは、その中で最も有名なのが「電磁誘導の法則」という、ファラデーの電磁誘導の法則。これ、日付まで分かってます。1831年8月29日に、有名な三つの実験っていうのがあります。それで発見したのが電磁誘導の法則。これは、磁場の磁界変化が電気を作るという、そういうことです。この発明、発見はですね、発電機やモーターの原理ですから、今日われわれが電気文明といって、電気がない社会って考えられないわけですけど、それをもたらしたのがファラデーのこの日の実験だったんですね。
これはどういうのかといいますと、多分、小学校や中学校の理科の実験で皆さんやりましたよね。二つ回路が、コイルがあって、片方に電源があってですね、スイッチを■■。片方は、ここに流れる電流を測れるように電流計がある。このスイッチを入れたり切ったりすると、ここに電流が流れる。あるいはこのコイルを、スイッチを入れておいて動かす。下にやったり上にやったり、動かす。そうするとやっぱり電流が流れる。それからもう一つは、このコイルの代わりに普通の棒磁石を持ってきまして、これをこう動かしてみると。そうするとやっぱり電流が流れる。
で、これは、ファラデーの3種類の実験をして、彼は電磁誘導の法則っていうのを発見するわけですね。磁場が磁界変化をすると電流が流れるんだっていうことが分かるわけですが、この発見が電気文明を作った、要するに応用としてすごかったっていうだけではなくて、物理学の物の考え方、われわれの見方ですね。この宇宙■■。それを革命的に変えたんです。
なぜかっていうと、彼はこう動かして、これ、磁場とか電場とか今いいますけど、そのころは磁力線っていったんですけど、それが実際に存在するということを確信を持ったわけです。それまでは、クーロンの法則ってありますね。電気のプラスとマイナスがあって力が働きますとか、太陽と地球には力が、万有引力が働きますと。そういうのが17世紀、まあ、ニュートンが確立するわけですけど、考えてみたら不思議な話ですよね。「離れてるのにどうして力が働くんや」と。そうじゃなくて、こういう変化を起こしたときに、この磁場という、あるいは電場というのが実際に存在していて、それが力を及ぼす、電気を流すというものである。要するに、離れてて何か起こるっていうことはありえないんだと。周りの空間の性質を変えるということが、力を及ぼすことにつながるという考え方です。
これは「近接相互作用」といいますけど、今の言葉でいうと、場の考え方、場の理論ということですね。「電磁場」っていう言葉を使いますね。電場、磁場。そういう場の理論の考え方に基づいていて、それは、数学的になんかEとかBとかっていうのがあるんじゃなくて、空間に実在するという、そのことを彼は初めて確信したんです。それが今日のあれです。
物理って物の理(ことわり)
物理学っていう言葉はね、物理って物の理(ことわり)、あれですね。いちばん最初、福沢諭吉が「physics」というのを訳したときには、「究理」って■■ですね。究理っていうのは真理を究めるっていうことでしてね、じゃあ、生物学はどうなんやとかそういうふうになって、究理じゃちょっとあまりにもあれだというんで、「物理」っていう名前にしたんですけれど。それで、多分中国、漢字の名人か中国人が物理って、日本人のまねをしたのかどうか分かりませんけど、物理っていうとちょっと、今の考え方からすると少し狭いんですね。要するに物じゃないんです。空間の性質っていうのが非常に重要だというのが、現代の物理学の考え方なんですね。その点、それを初めて言ったのがファラデーであったということです。 だから、現代では重力っていうのは、重力場っていう物の考え方は、太陽があるおかげでこの辺の空間の性質が変わってると。それを地球が感じて力が働くというふうに考えられていますね。重力場というのがポイントだっていうことですね。空間の性質が重要だということです。で、ちょっと待ってよ。それがここに書いてありますね。電磁場の発見。空間の意味というのが、場の理論というのにつながっていきます。それを深く考えるっていうことが、この場の■■。

その次に現われたのは、マクスウェルですね。マクスウェルっていう人は、なんか音楽とかで有名なのかな。僕は知らないんだけど。音楽テープとか電池とかいろいろありますけど、全然関係ありませんね。マクスウェルは、当時、物理学とかそういう学問をやる人って、大体暇な人、お金持ちが多いわけですね、当然ね。マクスウェルは、もちろんスコットランドの貴族でという、別に仕事しなくても食っていける人でありましたが、この人は純然たる理論物理学者です。さっきのファラデーは実験物理学者ですけど、この人がしたことはですね、電磁波の予言です。電磁波が存在することを予言しました。光は電磁波であるということも、この人が初めて言ったことですね。1864年です。
で、さっきちょっと式が書いてありました。これ、Bっていうのは磁場なんですよね。微分っていうのは習ってます? 時間と共に変化する、どう変化するか。時間がたつとどう変わるかっていうのを、微分っていう言い方をしますね。傾きっていうんですか。dt、dB。これ、磁場の変化の割合が電場Eを作りますっていうのが、さっきのファラデーの電磁誘導の法則なんですね。で、彼は、いろんな磁場が今度逆に……。じゃない。電流を流すと磁場ができます。これ、アンペールの法則っていいますよね。で、そういう電磁気のいろんなクーロンの法則ですとか、これを全部まとめようとしたわけですが、どうもおかしいと。うまくいかないと。「電荷の保存」というんですけど、電荷は消えてなくならないという要請をしちゃいますと、どうも方程式が変だと。それを満足させるためには、こういう関係式を入れておかないといけない。要するに、電磁誘導と今度逆で、電場が時間変化すると磁場を作るというタームを、項を入れてやると、電荷の保存とかいろんなことが、みんな説明、合理的に説明できますということを発見しました。


 オープンコア講座2008年
オープンコア講座2008年